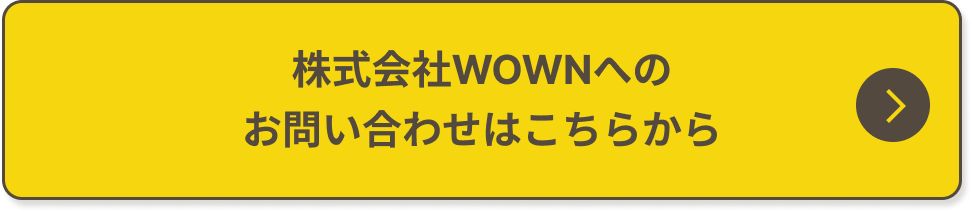「社内SNSを作ってはみたものの、なかなか盛り上がらなくて……」
そんな声を耳にすることがあります。もしかしたら、あなたの職場でも同じような状況かもしれません。最初は「気軽に意見を交わせる場にしよう」と始めたのに、ふたを開けてみると、発言するのは一部の人に限られていた。他の人は見ているだけで、発言してもスルーされてしまう……。
クローズドSNSで「情報共有」と「孤立感」の課題を解決【社内エンゲージメント向上】では、情報共有と孤立感の問題について取り上げました。今回はその続編として、“小さな場”をどうやって健全に育てていくか、という視点で掘り下げていきます。
目次
社内SNSでも起こる「発言しづらさ」と「孤独感」——その正体とは?
表向きには自由に投稿できる雰囲気でも、実際には“空気を読む力”が必要なんじゃないかと警戒してしまう。誰かの投稿がスルーされた過去を目にすると、自分もそうなるのではと不安に思う。そんなふうに感じている人は、少なくありません。
たとえばある企業では、業務の小さな気づきを社内SNSに投稿する取り組みを始めました。最初こそ盛り上がったものの、ある若手社員がちょっとした工夫を投稿した際、誰からもリアクションがつかなかった。それ以降、その社員は投稿しなくなり、周囲も「見てはいるけど、何を返せばいいのかわからない」と反応を控えるようになってしまいました。
「誰も見ていない」よりも、「見ているのに反応がない」ほうが、ずっと傷つくものです。
このような、意図がなくとも結果的にいじめのようになってしまう構造は、決して珍しいものではありません。クローズドな環境であるがゆえに起きる「見えない排除」こそ、運営側が最も気をつけるべきポイントです。
ファンマーケティングや地域コミュニティでも共通する課題とは?
こうした問題は、なにも社内に限ったことではありません。
ファンコミュニティや自治会などのグループでも、「何か言ったら浮きそう」「発言する人が決まっていて入り込みづらい」といった空気が生まれがちです。
たとえば、ファン同士が交流できるオンラインサロンを立ち上げた中小企業の事例では、初期メンバー数名のやりとりばかりが目立ち、新しく入った人たちは見ているだけ。発言しても返信がもらえず、ひとり、またひとりと発言する人が減ってしまったとのこと。
“メンバーはいるのに、空気と化してしまっている”コミュニティ、意外と多いものです。
小さな場を健全に保つには?——投稿ルールと“見守る人”の設計がカギ
そこで重要になるのが、投稿ルールと“見守る人”の存在です。
まず、場の目的やトーンに合わせた「投稿ガイドライン」を用意しましょう。 たとえば「批判ではなく提案の形で書く」「誹謗中傷や個人攻撃は禁止」「差別や性的な話題など、不快に感じる人がいる話題は投稿しない」など、基本的なマナーを明文化するだけでも、安心感はぐっと高まります。
また、政治や宗教といった意見の分かれやすい話題は、避けるようにするのが無難です。頭ごなしに禁止するのではなく、あらかじめテーマを決めておき、それに沿った投稿を促すようにしてもいいでしょう。
そして何より大切なのが、“見守る人”の存在。いわゆるモデレーターです。といっても、「ルールを取り締まる警察」のような存在ではありません。
こんなモデレーターがうまくいく——「警備員」ではなく「話しかけやすい係」に
モデレーターの役割は、空気を整え、言葉にしづらい違和感を拾うことです。
たとえば誰かの投稿がスルーされていたら、さりげなく反応する。新しいメンバーが入ったら、過去の投稿を引用して「この話題、興味ありそうですね」などと話を振ってみる。
また、投稿に対してスタンプなどのリアクションを積極的に行うことも、モデレーターの大切な役目です。最初は文化として根づいていなかったとしても、モデレーターが率先することで、他のメンバーも追随しやすくなります。そのSNS独自の文化が醸成されるまでの“頑張りどころ”といえるでしょう。
ポイントは、「上から目線ではないこと」。同じ目線で関わる“話しかけやすい係”のような存在が、場の継続には不可欠です。
ネガティブ投稿や炎上を防ぐには?——運営ルールの整備と普段の関わり方
あわせて検討しておきたいのが、誰かが傷ついたと感じたときに安心して声をあげられる仕組みです。
たとえ発言者にまったく悪気がなかったとしても、受け手によっては「その言い方がきつく感じた」「自分を否定されたように思った」と傷ついてしまうケースはあります。
そうしたとき、信頼できるモデレーターや相談窓口があるだけで、メンバーの心理的安全性は大きく高まります。たとえば「モデレーターに個別メッセージで相談してもOK」「気になる投稿があったら運営に知らせられるボタンがある」といった仕組みがあると、運営側も早期に気づいて対応することができます。
荒らしやネガティブ投稿を未然に防ぐ仕組みを作ることができれば、場の雰囲気が悪くなることはなく、運営の負担もぐっと減ります。
まずは、ガイドラインとして「批判ではなく提案に」「相手の人格ではなく行動にフォーカスする」など、具体的な書き方を提示すること。
さらに、普段からのコミュニケーションの積み重ねも重要です。モデレーターが丁寧な返信を心がけたり、場のトーンをフラットに保つことで、攻撃的な投稿をしづらい雰囲気が自然と生まれていきます。
“荒らし”やネガティブ投稿が起きたら?運営ができる3つの具体的対処法
どれほど注意していたとしても、問題の発生を完全に防ぐことは困難です。すべての投稿が好意的とは限らず、批判やクレーム、時には荒らしのような投稿もあるでしょう。
そのとき、次の3つのステップが役立ちます。
- 即座に反応せず、冷静にログを残す
- 非公開の場で個別に連絡し、意図を確認する
- ルールに沿った対応(投稿の一時非表示や注意)を行う
感情的にならずに、「場を守るための行動」であることを説明し、透明性をもって対応しましょう。
疲れない運営体制とは?——「誰か一人に頼らない」設計と心理的安全性の重要性
運営の負担が特定の人に偏ると、その人の負担は大きくなります。燃え尽きる前に、役割分担やローテーション制を取り入れることが大切です。
また、運営者自身も「完璧でなくていい」という空気を持つこと。ときには「これはどうすればいいと思う?」とメンバーに問いかけることで、一緒に場をつくっていくという感覚が育ちます。
社内・ファン・自治会……それぞれに合った“クローズドSNS設計”の考え方
大切なのは、「誰のための、どんな場なのか」を明確にすることです。
社内であれば業務の共有、ファンであれば共通の好きなもの、自治会であれば地域の課題など、それぞれに目的があります。
その目的に合わせて、投稿ルールやモデレーターの関わり方も変わってくるでしょう。
“小さな場”であっても、誰かにとっては“大切な場所”なのです。
その場が長く続くために、無理なく、そして少しだけ丁寧に、設計していきたいものですね。
(アイキャッチ画像:Designed by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください