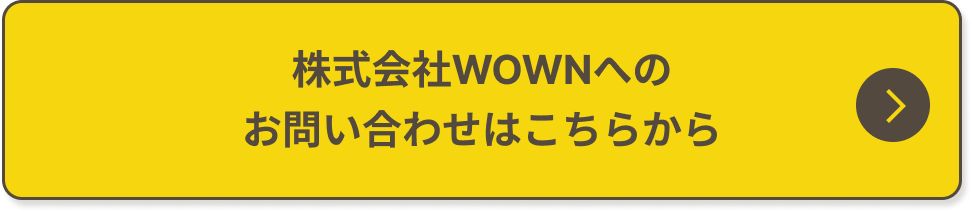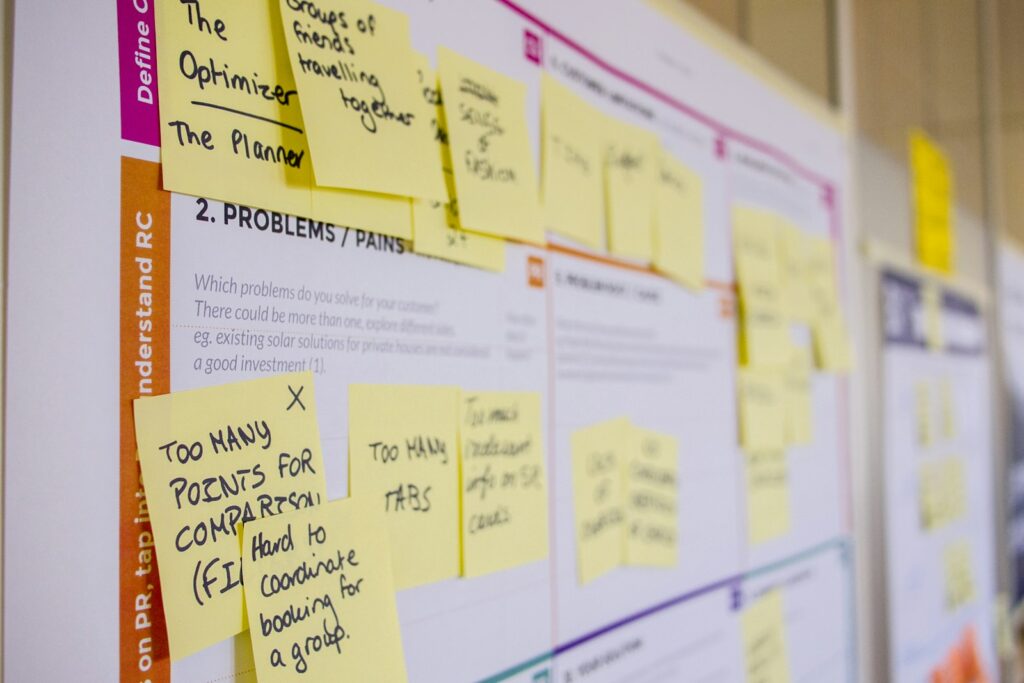「最近SNSがしんどい…」そんな声を耳にしたことはありませんか?
投稿しても反応が薄い、フォロワー数が増えても売上につながらない。中の人が頑張っても限界を感じる。
そんな“SNS疲れ”は、企業側にも、ユーザー側にも広がっています。
SNSマーケティングが当たり前になり、期待したほどの効果が得られなくなっている今は、次の一手を考えるべき転換期といえるでしょう。
転換の鍵となるのが、「クローズドSNS」という選択肢です。
オープンSNSにはオープンの良さがありますが、限界を感じることがあるのもまた事実。そこで今回は、オープンSNSの限界とクローズドSNSの可能性、そして自然に“濃いつながり”へ誘導する導線設計の考え方をご紹介します。
今すぐ施策に落とし込めなくても大丈夫。読み終えたとき、「なるほど、こういう考え方もあるんだ」と感じていただければ幸いです。
目次
オープンSNSの“限界”が見えてきた?中小企業に起きている変化
SNSは、企業にとってもユーザーにとっても“便利なつながりの場”でした。
特に中小企業にとって、無料で始められて拡散力もあるSNSは、強力なマーケティング手段となってきました。
とはいえ、最近は「つながりはできるけれど、その先が続かない」「フォロワーは増えたけれど、本音までは拾えない」といった課題を感じる企業も増えてきました。
X(旧Twitter)やInstagramといったオープンSNSには「出会いを生む」「検索に強い」「幅広い層に届く」などの良さがあり、出会いやきっかけづくりにおいては強力な力を発揮するツールです。検索性が高く、思いがけない接点を生む可能性も秘めています。
しかし一方で、炎上リスクやアルゴリズムの変化、発信へのハードルなどが影響し、深いつながりを築くのが難しいと感じるケースもあるでしょう。
最初の接点づくりには有効。ただし、関係性を深める場所としては向いていない。これが、今多くの企業が感じ始めている“限界”ではないでしょうか。
きっかけづくりはオープンで、深いつながりは別の場所で――そんな設計を考える時期が来ているのかもしれません。
「濃い話はこっちで」式導線設計――クローズドSNSで深める関係性
オープンSNSはあくまで“入口”。
そこから一歩進んだ“関係性を深める場”として注目されているのが、クローズドSNSです。
たとえば、オープンSNSでの投稿にこんなひと言を添えてみるとどうでしょうか?
「もっと詳しい話は、メンバー限定の○○でお話ししています」
「○月の企画の舞台裏は、クローズドグループで公開中です」
こうした言い回しは、情報を小出しにしながら「向こうにもっと面白い話があるかも」と期待を高めてくれます。
大切なのは、“売り込み”ではなく“誘い水”としての設計。
たとえば、「新しいキャンプギアを一緒に開発しませんか?」「フルマラソン完走を目指すためのシューズについて、語り合いましょう」「子育てに役立つアプリを一緒に考えてみませんか?」といった呼びかけが、参加への期待感やワクワク感を引き出す“誘い水”となります。
「興味がある方だけ、こっそりどうぞ」という雰囲気をつくることで、強制感のない自然な導線ができるのです。
導線設計とは、大げさな仕掛けではありません。
オープンSNSの中に、さりげない“別の扉”を設けること。それだけで関係性は一段深まります。
“安心して話せる場所”が鍵になる!SNS疲れ時代のクローズド活用法
オープンSNSでは、誰が見ているかわからない。
ちょっとした発言が誤解されたり、炎上したり……企業もユーザーも、どこか“発信疲れ”しています。
その反面、クローズドSNSは“誰とつながっているのかが明確”であり、“一定のルールや空気感”があります。
この安心感が、参加者の本音を引き出しやすくしてくれるのです。また、クローズドな場には“アンチ”や心ないコメントが入り込みにくいため、心理的な安全性が保たれやすいという特徴もあります。
発言者の顔が見えやすく、匿名性が低いこともポイントです。実名やプロフィールが明確な空間では、無責任な発言が減りやすく、安心して本音を語れる土壌が育ちます。
マーケティングの世界でも、同じことが言えるのではないでしょうか?
オープンな場では言えないけれど、クローズドな場所だからこそ語れること。
そんな“本音の交流”が、信頼を生み、やがてファンを育てていくのです。
「参加したくなる仕掛け」を用意する――限定性・イベント・双方向性の活用
クローズドSNSの価値を高めるうえで欠かせないのが、「参加したくなる仕掛け」です。
たとえば以下のような企画は、参加者の心をくすぐります。
- 限定ライブ配信(製品の開発秘話や裏話など)
- メンバー限定の投票やアンケート
- オンラインイベントや座談会の開催
- スタッフとの直接交流コーナー
- 新商品の共同開発
こうした企画があることで、「見るだけの場」ではなく「参加したくなる場」になります。
ポイントは、“やって終わり”にしないこと。
参加者の声を拾い、次につなげることで、クローズドSNS内に“居場所”が生まれます。
人は、参加した経験がある場所に愛着を持ちます。
「ここは自分も関われる場所だ」と感じられれば、自然とロイヤルティ(愛着心)も育まれていきます。
導入障壁を下げるには?最初の一歩を後押しするコミュニケーション設計
とはいえ、クローズドSNSに誘導しても「登録が面倒」「どんな人がいるのかわからない」と感じてしまうと、離脱の原因になります。
そこで大切なのが、参加までの“心理的ハードル”を下げる工夫です。
- 登録前に雰囲気がわかる紹介投稿を用意する
- スタッフの顔や自己紹介を見せて「誰がいるのか」を明示する
- 初心者向けのガイドや“はじめての方向けの部屋”を設ける
- 無料体験期間や限定公開を用意する
こうした設計があると、「とりあえず入ってみようかな」という気持ちが生まれやすくなります。
また、返信やリアクションのスピードも大事です。
「ちゃんと見てもらえている」と感じられれば、その場に安心感が生まれます。
クローズドSNSは、ただの“機能”ではありません。
そこにいる“人”と“雰囲気”が、最大の価値なのです。
まとめ|つながりを育てるSNS設計とは?
SNSマーケティングに正解はありません。
けれど、「どうすればもっと深くつながれるか」と考えることで、次の一手が見えてきます。
オープンSNSで“出会い”をつくり、クローズドSNSで“関係性”を育てる。
そんな設計が、これからの時代に求められるSNS活用ではないでしょうか。
焦らず、無理せず、できるところから。
「ちょっと試してみようかな」そんな気持ちで一歩踏み出すことが、未来のファンづくりにつながっていくはずです。
次回は、クローズドSNSで“語りたくなる体験”を設計する方法についてお伝えする予定です。
(アイキャッチ画像:Designed by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください