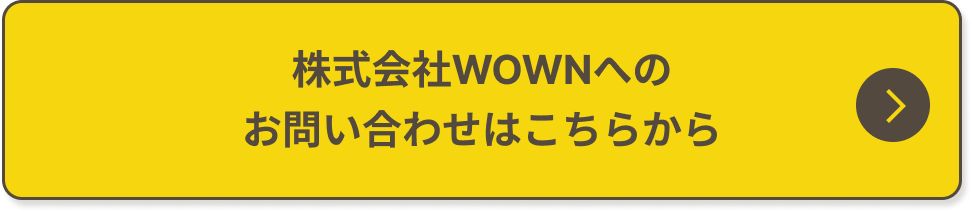クローズドSNSは、「SNS疲れ」や「本音が言えない」日常に対する処方箋のような存在です。本記事では、オープンSNSとの違いや、企業での活用事例を交えてその魅力を紹介します。
かつてSNSは、気心の知れた友人や知人とのやりとりが中心で、ある程度“閉じた”安心感のある場でした。
しかし、時代とともに誰とでもつながれる“オープンなSNS”が主流となり、情報の発信力が格段に高まる一方で、「反応が怖い」「誰に見られているかわからない」といった不安の声も増えてきたように感じられます。そうした中で、今あらためて注目されているのが「クローズドSNS」。その背景を、SNSの変遷とともに見ていきましょう。
目次
SNSの変遷:つながり方の変化
■ 2000年代前半〜
日本でSNSが広がりはじめたのは、招待制の「mixi」が登場した頃から。当時は本名でなくハンドルネームが一般的で、知人に招かれて参加するスタイル。結果として、投稿には自然と“本音”が出やすく、どこか穏やかで安心感のある空間が広がっていました。
■ 2010年代
Twitter、Instagram、Facebookが普及し、一気に“誰とでもつながれる時代”に。投稿は全世界に届き、いいねやフォロワー数が可視化されることで、発信のモチベーションも大きく変化しました。
拡散力の強さは大きな魅力である一方、炎上や誤解の拡散など、リスクも急増。「気軽に本音をつぶやけなくなった」という声が聞かれるようになります。
■ 2020年代
コロナ禍を経て、「安心して話せる場所」へのニーズが高まりました。家族や職場、地域コミュニティなど、限定されたつながりを再評価する動きが加速。SlackやDiscord、オンラインサロンといった、参加者が限定された空間=クローズドSNSに注目が集まっています。
総務省の調査でも、2022年以降SNS利用者の約7割が「閲覧範囲を制限して投稿している」と回答しており、安心感を求める傾向が強まっていることがわかります(出典:総務省 令和5年版 情報通信白書)。
オープンSNSとクローズドSNSの違い
オープンSNSとクローズドSNSの違いは、以下のように整理できます。
オープンSNSの特徴
- 参加範囲:誰でも参加・閲覧可能
- つながり方:フォロワー数や拡散が重視される傾向
- 投稿の心理的負担:炎上や誤解のリスクがある
- 情報の流れ:拡散されやすく制御しにくい
クローズドSNSの特徴
- 参加範囲:招待制や会員制などで限定
- つながり方:継続的な関係性を育てる
- 投稿の心理的負担:安心して発信しやすい
- 情報の流れ:コントロールがしやすい
たとえば、オープンSNSでは非公開設定にしても、知らない人から突然フォローされたり、過去の投稿が意図せず拡散されたりすることもありますよね。
一方で、完全に“鍵”をかけてしまうと、今度は友人を見つけづらいという不便さが出てきます。つまり、どこかに「ちょうどよい距離感」を求める気持ちがあるわけです。
巨大なオープンSNSには、思いがけない出会いや発見があります。たとえば、20年以上前に付き合いがあった学生時代の友人と、Facebookを通じて再びつながることができたという体験を持つ人もいます。しかしその反面、ちょっと息苦しさを感じたり、警戒感を抱いてしまったりする、という声も確かに存在します。
そして、そんな声に応える形で、クローズドSNSは存在感を増しています。
▶︎安心して繋がれるクローズドSNS「FAZZY」を見てみる。
安心感とコントロールしやすさがもたらすもの
クローズドSNSの魅力は、「炎上しない」ことではありません。
本当の強みは、投稿や会話のトーンを“コントロールしやすい”点にあります。たとえば、投稿に対して事前の承認制を設けたり、参加者に一定のルールを設けたりすることで、場の雰囲気を保つことができます。
共通の空気感のなかで発言できるため、意見のすれ違いや誤解が起きにくいという安心感があるからこそ、参加者は本音を語りやすくなり、率直な意見やアイデアも自然と出てきます。
企業や店舗にとっては、顧客やファンと信頼関係を築くための「裏側の声を拾える場所」としても活用の幅が広がっているように感じます。
クローズドSNSの活用シーン
実際に、クローズドSNSはさまざまな場面で活用されています。
- 製品購入者限定のコミュニティ
使用感や改善要望を自由に投稿できる場として、企業の製品開発に貢献。 - 地域イベントの参加者グループ
一度の参加で終わらず、その後のつながりや次回の参加につなげる仕組みに。 - NPOの支援者向けSNS
活動報告を通じて、支援者との距離を縮め、共感を深める場として活用。 - 小規模店舗の常連顧客グループ
新メニューの試食会情報や、裏話の共有を通じてファン化を促進。 - 企業内の社員コミュニティ
部門を越えた意見交換や、ナレッジ共有の場として活用。 - 学校関係者向けのクローズドSNS
保護者連絡や、学校行事・学級運営の情報共有など、安心感のあるつながりに。
いずれも共通しているのは、「つながりたい」「声を届けたい」という気持ちが前提にあること。クローズドSNSは、その思いを育てる“場所”として選ばれているのです。
まとめ:あえて“閉じる”という選択肢
これまでSNSは、いかに広く、速く、多くに届けるかを競う場でした。
でも、これからは「誰と」「どうつながるか」が、ブランドの信頼やファンとの関係性に直結する時代。クローズドSNSは、そんな時代に合った“つながりのデザイン”ともいえるのではないでしょうか。
すべての発信が“見られる前提”であるオープンSNSに疲れてしまった方にとっても、「あえて閉じる」ことで、もっと自由に、もっと誠実にコミュニケーションできる可能性が広がっています。
もし、今のSNS運用に違和感や限界を感じているのであれば——クローズドSNSという選択肢があることを、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。
次回は、クローズドSNSへの導線設計術というテーマでお送りする予定です。
(アイキャッチ画像:Desgined by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください