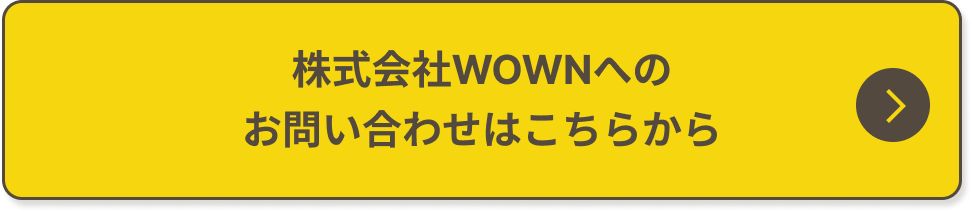会社組織に身を置く以上、他の社員との連携なしに業務を進めることはできないもの。連携がうまくいかずに業務が滞ってしまって困った経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
業務が滞る原因として考えられるのは、
- 特定の人物の知識やスキルに依存しており、業務の標準化が進んでいない(業務のブラックボックス化)
- 情報が共有されていない
- コミュニケーション不足
- 人手不足
などですが、とりわけ情報共有が十分になされない状況、コミュニケーションが不足している状況に、人は大きなストレスを感じます。こういった状況は社員の孤立感を招き、離職にもつながりかねません。
そこで注目したいのが、クローズドSNSの社内活用です。オープンSNSのように外部に公開されることがなく、社員だけが安心して利用できる空間であるため、社内での円滑な情報共有が可能になり、良好な人間関係が育まれる土台にもなります。
今回は、「社内エンゲージメント向上」「情報共有の壁」「心理的安全性」などをキーワードに、クローズドSNSが果たす役割について解説します。
目次
情報共有できない職場は「孤立」と「離職」を生む
社内エンゲージメントの低さは、業務フローだけでは解決できません。なぜなら、業務の手順や仕組みが整っていても、日々のコミュニケーションが不足していれば、現場では情報の行き違いや不満が生じやすく、社員のモチベーション低下につながってしまうからです。
たとえば、以下のような声に心当たりはないでしょうか?
「上司の指示がメンバーに伝わっていない」
「他部署で何が起きているか分からない」
「新人が定着せず離職してしまう」
「実はわからないけど、今さら聞けない……」
こうした声の多くは、『情報共有の壁』――つまり、必要な情報が必要な人に届いていない状態――によるものです。属人化が進み、限られた人だけが知識を持っている状態では、チーム全体のパフォーマンスも上がりません。
「話せる・聞ける・共有できる」空気がなければ、いくら制度を整えても社員のエンゲージメントは高まりません。
社員の声が届かない──中小企業が抱える情報共有の壁
中小企業では、人数が少ないからこそ“全員が把握している”と思われがちです。しかし実際には……
- 非常勤・パートスタッフとの情報格差
- リーダー層ばかりが発信する一方通行の情報伝達
- ITリテラシーのばらつきによる連絡ミス
こうした課題が、「伝えたつもり」「聞いていない」といったすれ違いを生み、エンゲージメント低下や誤解につながります。
この“壁”を乗り越えるには、階層や役職に関係なく「気軽に参加できる情報の場」を設けることが大切です。クローズドSNSはその受け皿になります。
心理的安全性のある職場が、社内エンゲージメントを育てる
心理的安全性とは、「この場で発言しても否定されない」という安心感のことです。これは、上下関係や部署の違いにかかわらず、誰もが自分の意見を出しやすい職場環境を意味します。発言のしやすさは、そのまま社内エンゲージメントの高さに直結します。
たとえば、面と向かってだと緊張してしまう新人の質問や、「今さらこんなこと聞けない」と感じているベテランの確認事項など、見過ごされがちな声もあります。クローズドSNSは、そうした“言いづらさ”をやわらげ、発言への心理的ハードルを下げるツールとして機能します。
アーカイブこそがSNSの強み
SNSの強みは、「流れて終わる」情報ではなく、蓄積される情報だという点です。投稿内容ややり取りがアーカイブされることで、後から入社した社員も「過去にどんなやり取りがあったのか」「どういう経緯でその方針になったのか」を自分で確認できます。これにより、新人が同じ質問を何度も繰り返す必要がなくなり、ナレッジの共有が仕組み化されていきます。過去のやり取りを俯瞰的に閲覧することもできて、組織全体の理解度や透明性も高まります。
組織の一体感を醸成
たとえば、全国に複数の事業所を持つ企業では、物理的距離によって教育や情報の質に差が出ることがあります。しかし、クローズドSNSを活用すれば、どこにいても同じ情報にアクセスでき、拠点間の“情報格差”が縮まり、組織としての一体感も高まるのです。
メールでは埋もれてしまいがちなやり取りも、SNSなら検索ができ、過去のやり取りを簡単に振り返り、学びに活かせます。伝えるだけでなく、蓄積して活かす──それがクローズドSNSの本質的な価値です。
社内SNSの導入で何が変わる?中小企業での活用法
たとえば、ある企業ではクローズドSNSを使い、日々の「ありがとう」や「頑張り」を投稿する取り組みを始めたことで、他部署間の交流が増えたという声があります。
また、新人の質問をSNSでオープンにすることで、ベテラン社員の知見が共有され、業務の属人化が解消されたという事例もあります。
こうした実践の積み重ねが、社内の雰囲気や働きがいに好影響を与え、「自分の頑張りが見てもらえている」と感じる人が増えたという声もあります。
社員の定着率を高める「雑談・共感・参加」の仕組み
「雑談はただの息抜き。仕事に関係ない」と思われがちですが、実は社員の定着率と大きな関係があります。
ちょっとした声かけや、他愛のないやり取りがあることで、チームの一員であるという実感が得られます。何気ない雑談ができることで、「自分はここにいていいんだ」という心理的安全性が高まり、チームワークも強くなっていくのです。
クローズドSNSは、業務連絡だけでなく、何気ない“雑談”にも使える交流ツールです。誕生日を祝う投稿、ランチの感想、趣味のシェア──わざわざメールで送るのは、はばかられますよね。そんな業務とは直接関係のないメッセージも、SNSならば気軽に送れます。そして、そのような何気ない交流が、人間関係を良好にして、離職を防ぐ“つながり”を育て、仕事のアイデアが生まれるきっかけにもなります。
クローズドSNSがつくる「つながり」が組織全体の士気を高める
クローズドSNSの活用により、部署間・役職間の壁を越えたコミュニケーションが活発に行われるようになると、社員同士の人間関係が良好になります。
日常的なやりとりが活発になることで、感謝や共感が可視化され、職場に前向きな空気が醸成されます。
こうした空気は、業務の質やスピードにも好影響を与えるだけでなく、組織全体の士気や一体感を高めることにもつながります。
職場の空気が前向きで、社員一人ひとりが充実感を持って働ける状態が続けば、その活力は自然と商品やサービス、顧客対応などにも表れます。結果として、会社全体の信頼性やブランド力の向上にもつながっていくのです。
どのSNSツールがいい?クローズドSNSの選び方ガイド
社内SNSを選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう:
- スマートフォンでも直感的に使える設計か(職種やITリテラシーに関係なく操作できるか)
- 投稿の公開範囲を細かく設定できるか(部署ごと、役職ごとなど)
- 通知やリアクションなどの機能が過不足ないか
- 定着のためのサポート体制があるか
安心して意見が言える文化を醸成するためには、ツールの使いやすさが大きなポイントとなります。社員が“つい開きたくなる”デザインや導線があるかも重要です。また、投稿しやすさや通知のタイミング、返信のしやすさなども、日常的に利用してもらうための重要な要素です。
まとめ|エンゲージメント施策の第一歩は「安心して話せる場づくり」から
社内エンゲージメントを高めるには、制度や仕組みの前に「社員が安心して話せる空気」をつくることが大切です。
クローズドSNSは、心理的安全性や情報の可視化・蓄積といった“安心して関われる環境”を整える土台を支えるツールのひとつ。情報共有の壁をなくし、社員の孤立を防ぐことで定着率が上がり、最終的には企業のブランド力向上にもつながります。
すぐに導入できなくても、まずは「いま、自社にはどんな声が拾えていないか?」を振り返るところから、始めてみてはいかがでしょうか。
次回は、コミュニティ運営のコツについてお伝えする予定です。炎上を防ぎ、クローズドSNSを良質なコミュニケーションの場とするためのポイントを考えていきましょう。
(アイキャッチ画像:Designed by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください